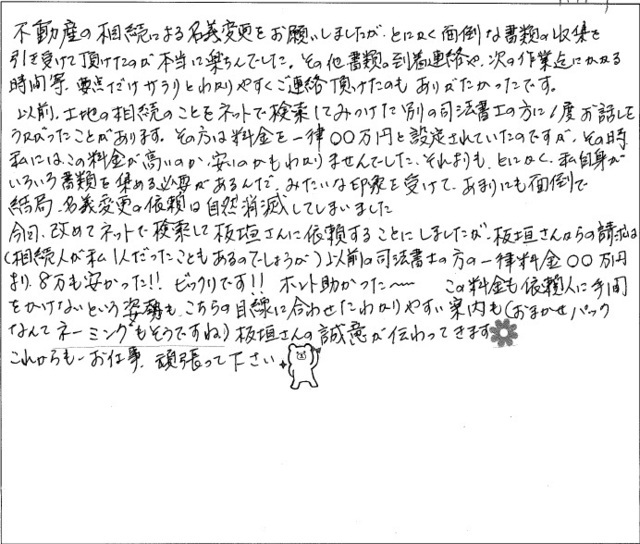親が亡くなって預金を相続する際、「いつまでに手続をしなければならないか」という疑問を持つ方は多いでしょう。
結論から言うと、預金相続には法律で定められた厳格な申請期限は原則ありません。しかし、だからといって「いつ手続きしても同じ」というわけではなく、放置すると様々なリスクが生じます。
本記事では、司法書士の実務経験から、預金相続で意識すべき「期限」を4つの視点で整理し、実際に目安とすべきタイムラインを解説します。
※預金相続の具体的な手続きの流れについては、【保存版】銀行預金の相続手続き|口座凍結後の流れ・必要書類を司法書士が解説をご覧ください。
預金相続に「申請期限」がない理由
不動産の相続登記のように「○年以内に申請しなければならない」という法律上の義務は、預金相続にはありません。
ただし、この「期限がない」という状況は、実務上は次のような意味を持ちます。
- 権利が消滅する危険性がゼロではない(時効の問題)
- 長期間放置すると、手続が複雑になる仕組みがある(休眠預金等の扱い)
- 他の相続手続との関係で、事実上のリミットが発生する
つまり、「いつでもいい」ではなく、「早く動いたほうが確実に有利」というのが実態です。
預金相続で意識すべき4つの「期限」
預金相続を考える際、次の4つの視点から「期限」を整理することが重要です。
1. 権利としての期限:消滅時効
預金は法律上「預金返還請求権」という債権です。一般の債権と同様に、消滅時効の対象になり得ます。
2020年の民法改正後、消滅時効の基本ルールは次のとおりです。
| 起算点の種類 | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 主観的起算点 | 5年 | 債権者が「権利を行使できること」を知った時から5年 |
| 客観的起算点 | 10年 | 権利を行使できる時から10年 |
実務上、金融機関が時効を主張するケースは聞いたことがありません。しかし、これは「時効がない」という意味ではなく、金融機関の運用方針によるものです。法的リスクとしての時効は存在することを理解しておく必要があります。
2. 制度としての区切り:休眠預金等活用法
休眠預金等活用法では、10年以上入出金などの取引がない預金が「休眠預金等」として扱われます(2009年1月以降に最後の異動があった預金が対象)。
休眠預金等になったからといって、預金が「没収」されるわけではありません。引き出しは可能で、引き出しの期限もありません。
ただし、通常の口座よりも手続に時間がかかったり、窓口での対応が必要になるなど、事務手続の負担が重くなる可能性があります。
3. 周辺制度の期限
預金相続そのものに期限はなくても、関連する他の手続には厳格な期限があります。
- 相続放棄の熟慮期間:3か月以内(相続開始があったことを知った時から)
- 相続税の申告期限:10か月以内(相続の開始があったことを知った日の翌日から)
- 相続登記の申請義務:3年以内(自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から)【2024年4月から義務化】
これらの期限に間に合わせるためには、預金残高の確定や遺産分割協議の完了が必要になる場合があります。つまり、他の手続の期限が、事実上の預金相続の期限となるのです。
4. 実務上の限界期限
法律上の期限以上に問題となるのが、実務上の難度が上がる局面です。
- 数次相続:相続人が亡くなってさらに相続が発生すると、関係者が増えて協議が困難に
- 認知症:相続人が意思能力を失うと、成年後見人を立てる必要があり、時間と費用が増大
- 印鑑証明書の期限:金融機関は「発行後3か月以内」などの運用をしており、再取得が必要になる
これらの問題は、時間が経つほど確率が高くなります。
実務上の目安:いつまでに手続すべきか
法律上の「絶対期限」はありませんが、実務的には以下のタイムラインを意識することをお勧めします。
| 時期 | やるべきこと |
|---|---|
| 相続開始から3か月以内 | 負債調査、相続放棄の可能性を判断。預金の引き出しは慎重に検討 |
| 相続開始から10か月以内 | 相続税申告の要否を判断。預金残高を確定し、遺産分割協議を進める |
| 相続開始から1年以内 | 預金解約・名義変更を含め、主要な相続手続を完了させる |
この目安は法的義務ではなく、実務リスクを最小化するための現実的な設定です。特に、相続人が高齢である場合や、相続財産が複雑な場合は、早めの着手が重要になります。
口座凍結と仮払い制度
口座凍結のタイミング
金融機関が口座名義人の死亡を知ると、預金口座は「凍結」されます。ただし、これは死亡届と自動的に連動するわけではなく、実務上は次のような経路で金融機関が把握します。
- 相続人からの連絡
- 残高証明書の請求
- 相続手続の照会
凍結されると、ATMでの引き出しや口座振替が停止されるため、公共料金などの支払い方法を早急に変更する必要があります。
遺産分割前の仮払い制度
2019年の民法改正により、遺産分割が完了する前でも、一定額を単独で払い戻せる「仮払い制度」が設けられました。
単独での払戻可能額 = 相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 当該相続人の法定相続分
同一金融機関あたり上限150万円(全支店合算)
この制度は、葬儀費用や当面の生活費を確保するための「つなぎ」として有効です。
※仮払い制度の詳細については、預貯金の仮払い制度で詳しく解説しています。
口座凍結前にキャッシュカードで預金を引き出して葬儀費用に充てるケースがありますが、相続放棄の可能性がある場合は特に注意が必要です。
相続財産の処分と評価されると、法定単純承認(民法921条)に該当し、相続放棄ができなくなる可能性があります。
負債が疑わしい場合は、原則として預金に手を付けず、やむを得ず支出する場合は領収書を厳格に保管しましょう。
※相続放棄の手続きや注意点について詳しくは、【相続放棄と相続登記の完全ガイド】手続き・費用・注意点をご覧ください。
預金相続の実務手続フロー
必要書類(標準セット)
金融機関によって差はありますが、一般的に次の書類が必要です。
- 被相続人:出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人:現在戸籍
- 遺産分割協議書(または遺言書・家庭裁判所の書類)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 通帳・キャッシュカード・届出印(紛失時は所定手続)
※必要書類の詳細については、預金の相続手続きに必要な書類一覧|金融機関での手続きガイドをご参照ください。
印鑑証明書の有効期限に注意
不動産登記と異なり、金融機関の実務では印鑑証明書に「発行後3か月以内」「発行後6か月以内」などの独自の運用があります(金融機関により異なります)。
手続を長期化させると、最初に揃えた証明書が使えなくなり、相続人全員に再取得を依頼することになります。ここで協力が得られず、手続が止まってしまうケースは珍しくありません。
法定相続情報一覧図の活用
法定相続情報一覧図を取得しておくと、戸籍の束を複数の金融機関に持ち回る必要がなくなり、複数の金融機関への手続を同時並行できます。
相続人が多い場合や、取引していた金融機関が複数ある場合に特に効果的です。
※法定相続情報一覧図の取得方法やメリットについては、【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?で詳しく解説しています。
放置が招く実務リスク
数次相続で当事者が増える
一次相続の手続中に相続人が亡くなれば、二次相続が発生します。すると、
- 当事者の人数が増加
- 関係が希薄化(面識なし・疎遠な親族が加わる)
- 海外居住や所在不明の相続人が混入
といった問題が生じ、遺産分割協議の成立が一気に難しくなります。
認知症で協議が組めなくなる
遺産分割協議は法律行為であり、意思能力が必要です。高齢の相続人が認知症などで意思能力を失うと、成年後見人を立てる必要があり、時間と費用が大幅に増加します。
「期限がない」からこそ、このリスクが実務上の最大のボトルネックとなります。
相続税申告期限との衝突
預金手続に法定期限がなくても、相続税申告には厳格な期限(原則10か月)があります。預金残高の確定が遅れると、申告の精度や各種特例の適用に影響します。
場合によっては、未分割申告や「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要になり、税理士との連携が不可欠です。
※相続税の基礎控除や申告が必要なケースについては、相続税とは?かかる人・かからない人の違いで詳しく解説しています。
専門家活用のタイミング
司法書士が関与できる範囲
司法書士は、相続人の依頼に基づき、以下の業務を行うことができます。
- 戸籍収集・相続関係説明図/法定相続情報一覧図の作成
- 金融機関手続の段取り・書類作成支援
- 遺産承継業務としての預金解約等の手続代行
ただし、相続人間で利害対立が強い(紛争性が高い)場合は、弁護士対応が適切となるケースもあります。
費用対効果の考え方
専門家費用は自由報酬ですが、一般に「最低報酬+財産比例」という設計が多く見られます。
「自分でできるか」ではなく、次の観点で判断すると納得感が高まります。
- 平日昼間に何度も動けるか
- 相続人が何人で、協力が得られるか
- 取引していた金融機関が何行あるか
- 税務や生活費の面で期限に追われているか
預金相続には法律上の厳格な申請期限はありませんが、放置することで静かに不利を積み上げる性質があります。
時効のリスク、休眠預金の扱い、数次相続や認知症によるリスクなどを考慮すると、相続開始後できるだけ早期に、遅くとも1年程度を目安に主要な預金手続を完了させることが現実的です。
「期限がない」は安心材料ではなく、「設計しないと長期化する」という意味です。早い段階で全体像を把握し、必要に応じて専門家を活用することが、最も安全で負担の少ない進め方と言えます。