不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
相続登記に必要不可欠な戸籍謄本とは
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年11月25日
戸籍謄本とは?
戸籍謄本とは?
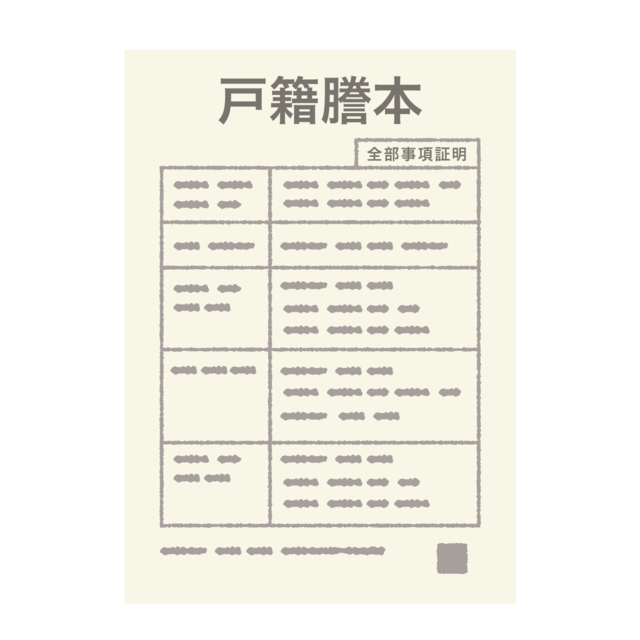
戸籍謄本とは、戸籍の全部事項証明書のことを指します。
戸籍とは、日本国民の出生、婚姻、死亡などの身分関係を登録し、明確にするための公的な記録です。この戸籍を原本として、記録されている内容を全てコピーしたものが戸籍謄本です。現在は戸籍が基本的に電子化されていますので、電子化されたデータの証明書として発行されるのが「戸籍の全部事項証明書」です。電子化される前は、紙戸籍を謄写していたので戸籍謄本と呼ばれていましたので、現在も登記簿謄本と呼ぶのが一般的です。
戸籍は、夫婦とその未婚の子どもを単位として編成されます。夫婦は必ず同じ戸籍になります。夫婦の間に子どもが生まれると、夫婦の戸籍に入ります。結婚すると、両親の戸籍から抜けて、夫婦の戸籍が作られます。
戸籍謄本には、その戸籍に記載されている全員の情報が記載されています。具体的には、本籍地、筆頭者、氏名、生年月日、父母の名前、婚姻・離婚などの情報が記録されています。
戸籍は、日本国民であることを証明する重要な書類の一つであり、様々な行政手続きや法律行為において必要とされます。例えば、相続手続き、不動産登記、パスポート申請などで提出を求められることがあります。
戸籍制度は、日本の社会において、個人の身分関係を明確にし、法的安定性をもたらす上で不可欠な役割を果たしています。
改製原戸籍とは?
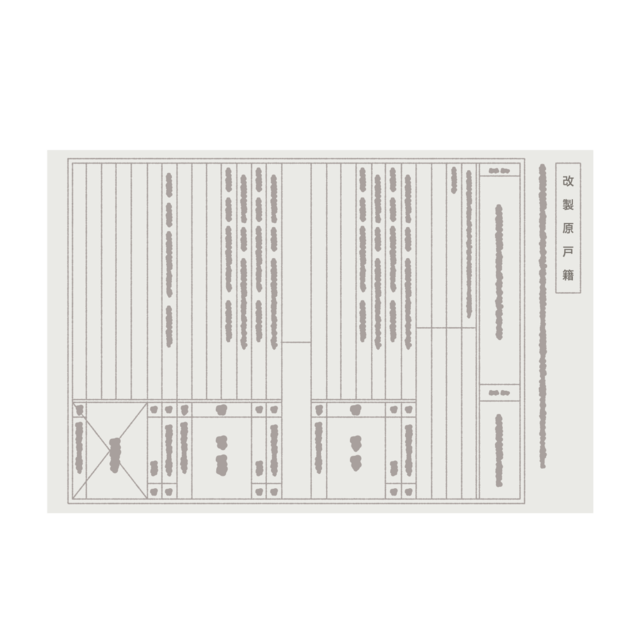
改製原戸籍とは、法律の改正により戸籍の様式等が変わり新しく作り直された場合の、前の古い戸籍になります。原戸籍とも呼ばれます。
戸籍は法律の改正により過去に何度か作り替えされています。直近ですと平成6年に電子化されるようになり、それまで横書き(B4サイズ)だったものが、横書き(A4サイズ)に変更となりました。
改製原戸籍の記載内容等は戸籍謄本と同じです。改製原戸籍は過去の戸籍の履歴になりますので、主に相続手続きに利用されます。相続の際は被相続人の出生から死亡までの戸籍の追跡が必要となりますが、基本的には改製原戸籍も手続きに必要となります。
除籍謄本とは?
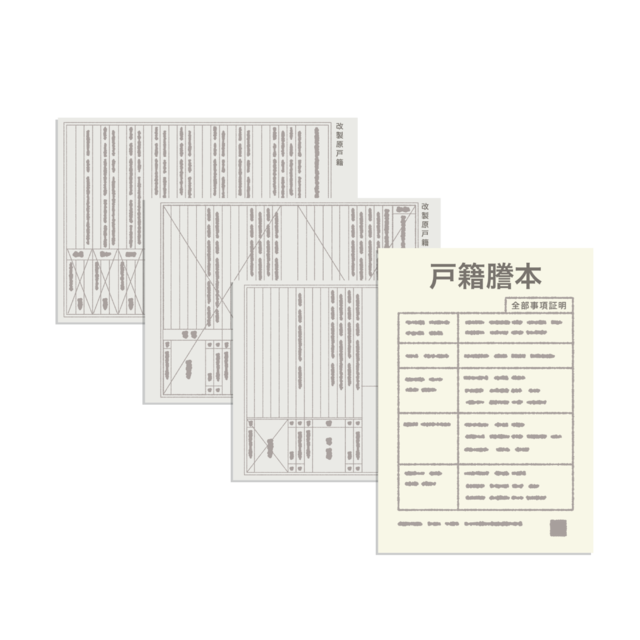
除籍謄本とは、戸籍内の人が転籍や死亡して全員が除籍された戸籍の写しのことです。電子化された後に除籍されたものは除籍全部事項証明と呼ばれます。
除籍謄本の記載内容等は戸籍謄本と同じです。除籍謄本は改製原戸籍と同様に過去の戸籍の履歴になりますので、主に相続手続きに利用されます。被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を全て揃えることによって相続関係を証明できます。
出生から死亡までの戸籍を揃えるのに除籍謄本や改製原戸籍については各1通あれば揃うものではなく、人によってそれぞれ何通があるのかどうかも異なります。
相続の費用の無料相談はこちら
戸籍謄本に記載されている内容
戸籍謄本には、個人の身分関係を証明するために必要な情報が網羅的に記載されています。
具体的には、以下の情報が含まれます。
- 本籍地
戸籍が置かれている場所を示すもので、住所とは異なります。戸籍は本籍地の市区町村で管理されます。 - 筆頭者の氏名
その戸籍の最初に記載されている人のことで、筆頭者が死亡しても筆頭者に変更はありません。婚姻時に夫婦の氏を、夫の氏とした場合は夫が筆頭者、妻の氏とした場合は妻が筆頭者になります。 - 戸籍事項
その戸籍が作られた年月日と原因が記載されます。その戸籍が消除された場合はその年月日と原因が記載されます。 - 戸籍に記録されている者
戸籍に記載されている人それぞれの氏名、生年月日、父母の氏名と続柄、出生地、死亡に関する情報が記載されます。 - 身分事項
出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、廃除に関する情報が記載されます。
これらの情報は、個人の身分関係を公的に証明するために重要な役割を果たします。
戸籍謄本の取得方法と取得費用
戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本を請求・取得する方法はいくつかあります。
- 市区町村役所の窓口で申請
本籍地の市区町村役所の窓口で直接申請する方法です。この場合、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。窓口で申請書に必要事項を記入し、手数料を支払うことで戸籍謄本を取得できます。 - 郵送申請
本籍地の市区町村役所へ郵便で申請する方法です。この場合、ウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して、本人確認書類のコピーと手数料分の定額小為替を同封して郵送します。郵送の場合、通常、1週間から2週間程度で戸籍謄本が送られてきます。 - オンライン申請
インターネットを利用して申請する場合です。この場合、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要になる場合があります。オンラインで申請すると、郵送で戸籍謄本が送られてくるか、市区町村によっては窓口で受け取ることも可能です。 - コンビニエンスストア
コンビニで発行する方法です。この場合、マイナンバーカードが必要となり、マルチコピー機で申請・印刷します。ただし、コンビニ交付に対応している市区町村に限ります。
戸籍謄本の手数料
戸籍謄本を取得する際には、手数料がかかります。
戸籍謄本の手数料の金額は1通450円です。除籍謄本や改製原戸籍の場合は1通750円かかります。戸籍謄本を複数通取得する場合は、その通数分の手数料が必要になります。
窓口で申請する場合、現金やキャッシュレス等で支払うことができます。郵送で申請する場合は、手数料分の定額小為替を同封する必要があります。定額小為替は、郵便局で購入することができます。オンラインで申請する場合や一部の役所では、クレジットカードや電子マネーで支払うことができる場合があります。コンビニエンスストアで取得する場合は、マルチコピー機で現金または電子マネーで支払うことができます。
市区町村キャッシュレス郵送請求リンク集
広域交付制度
広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等を請求できる制度です。2024年3月1日の戸籍法の法改正により利用できるようになりました。
【広域交付のメリット】
- 遠方の本籍地のものも取得可能
本籍地が遠くにある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。 - まとめて取得可能
相続の際の戸籍等で、本籍地が全国各地にあっても1つの市区町村の窓口で請求できます。
【広域交付の注意点】
- 本人のみ請求可能
代理人による請求はできません。 - 窓口でのみ請求可能
郵送やオンラインでの請求はできません。 - 直系のみ請求可能
直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)の戸籍謄本は請求可能ですが、本籍地の異なる兄弟姉妹や叔父叔母の戸籍謄本は取得できません。 - 写真付き公的身分証明書が必要
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の顔写真付きの身分証が必要で、健康保険証などの顔写真の無い身分証では交付できません。 - 予約が必要な場合がある
役所によっては事前に予約が必要な場合がありますので、請求先に事前に確認が必要です。 - 当日発行できない場合がある
役所の混雑状況によっては請求当日にすぐに取得できない場合があります。
【広域交付】戸籍謄本が全国どこからでも取得可能に
戸籍謄本が必要な場面
相続の手続き・相続登記
相続の手続きについては戸籍謄本が重要な書類となります。
相続の手続きをするためには、その人が亡くなったことの証明、その人の相続人が誰なのかの証明が必要になります。亡くなったことや、相続人が誰なのかを証明できるのが戸籍謄本です。
相続手続きの場合は、遺言書がある場合等を除き、基本的には亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までに作成された戸籍が全部必要になります。死亡の記載のある最後の戸籍はもちろん、出生時に最初に登録された際の戸籍や、法律の改正で閉じられた戸籍(改製原戸籍)、全員除籍で閉じられた戸籍(除籍謄本)なども全て必要になります。
被相続人の出生から死亡までを揃えることで相続人が確定します。被相続人の配偶者が誰で、子が何名いるのが、認知や養子がいないかも基本的に全て把握できます。
相続による不動産名義変更(相続登記)の場合も、相続手続きの1つですので、当然上記の戸籍謄本は必要になります。
【相続登記の必要書類一覧表】詳細まとめ・ダウンロード可
遺言書作成(公正証書遺言)
公正証書遺言書を作成する際は、遺言書を作成する前提として、推定相続人の確認が必要となります。相続関係の正確な把握のためには戸籍謄本が必要となり、基本的には公証役場にも戸籍謄本を提出することになります。
公正証書遺言とは?自分で進める流れや司法書士への依頼方法を解説!
結婚・離婚手続き(婚姻届)
以前は婚姻届や離婚届の提出時に、基本的には戸籍謄本が必要でしたが(本籍地へ届出する際を除く)、戸籍法の改正により令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、婚姻届提出時に、戸籍謄本等の添付が不要となりました。
なお、婚姻届・離婚届提出後に戸籍謄本が作成されるには、数日〜2週間程度の時間がかかります。
転籍・養子縁組
上記の婚姻届と同じく、。戸籍法の改正により令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、届出提出時に、戸籍謄本等の添付が不要となりました。
パスポート申請
パスポートの新規発給申請手続きや、切替発給申請手続きで戸籍上の身分事項に変更がある場合する際には、戸籍謄本が必要になります。
全部事項証明書(戸籍謄本)が必要で個人事項証明書(戸籍抄本)は使えませんのでご注意ください。
なお、令和7年3月24日から、全ての都道府県においてオンラインでのパスポート新規申請が可能となり、オンライン申請では、戸籍情報がシステム連携されるため、紙の戸籍謄本を取得し、提出する必要がなくなります。
相続登記に必要な戸籍謄本の収集
被相続人の戸籍は途切れなく「出生から死亡まで」を追跡
相続登記で最も重要なのは、被相続人の生涯にわたる身分関係を公的に証明し、他に隠れた相続人がいないことを確認することです。そのため、原則として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)を集めることが必須となります。
戸籍は法改正や本籍地の移転(転籍)によって形式が変わります。
被相続人が一生の間に本籍地を一度も変更していない場合は比較的簡単ですが、転籍を繰り返している場合は、すべての本籍地を辿って、それぞれの市区町村役場に請求を行う必要があります。実務上の困難は、「一つ前の本籍地」がどこだったかを確認する作業が煩雑なことです。この追跡は、取得した除籍謄本や改製原戸籍謄本の末尾(または付随情報)に記載されている「従前地」(一つ前の本籍地)の情報を頼りに行います。
つまり、最新の死亡時の戸籍から遡って、一つ前の本籍地を記載情報に基づいて特定し、その地を管轄する役所に請求するというプロセスを、出生時の戸籍に辿り着くまで継続しなければなりません。この連続した追跡作業が途切れたり、必要な戸籍が一つでも欠けている場合は、相続人確定の証明力が不足し、登記申請を進めることができません。
これらの改製原戸籍謄本や除籍謄本を、出生時のものから死亡時のものまで途切れなく集めることで、初めて法務局は法定相続人の範囲を完全に確定できるようになります。
被相続人の戸籍が複雑(転籍・除籍多数)な場合の収集手順
兄弟姉妹が相続人となる場合(両親の戸籍)
亡くなった人に子や孫がおらず、かつ両親や祖父母などの直系尊属(上の世代)もすでに亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合、兄弟姉妹が相続人であることを確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に加えて、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。
これは、直系尊属(両親)が確かに亡くなっていることを証明し、異父母の兄弟姉妹の存在の有無を確認するためです。両親の出生から死亡までを追跡することは、被相続人本人の追跡以上に複雑になることが多く、専門的な知識が求められる領域です。
よくあるご質問
戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?
戸籍謄本と戸籍抄本で証明される身分事項について違いはありませんは戸籍に記載した内容の全部・全員の証明です(全部事項証明)。戸籍抄本は戸籍に記載した内容の一部の証明です(個人事項証明)。
戸籍謄本と戸籍抄本で証明される身分事項の内容に違いはありません。全員の証明か、特定個人だけの証明なのかの違いだけです。
利用目的によって戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが必要かは異なりますが、基本的には戸籍謄本があれば戸籍抄本の内容も含まれることにはなります。
戸籍謄本と住民票の違いは?
戸籍謄本は身分や親族関係など証明書で、住民票は居住に関する証明書です。
戸籍謄本には住所は載りません。住民票には同居の親族等は載りますが、身分関係等の全てを把握することはできません。
戸籍謄本は本籍地、住民票は住所地の市区町村にて管理している違いもあります。
法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりになる?
法定相続情報一覧図は、相続手続きを簡略化するために法務局が発行するもので、亡くなった方の相続関係を図式化し登記官が証明したものです。
法定相続情報一覧図があれば、相続手続きの際に戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなり、手続きがスムーズに進みます。
しかし、法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の完全な代わりにはなりません。法定相続情報一覧図は、あくまで相続関係を証明するものであり、戸籍謄本に記載されているすべての情報が網羅されているわけではありません。
相続の手続きであれば基本的には法定相続情報一覧図が戸籍謄本等の代わりとして利用できますが、相続以外の手続きには基本的に利用できないと考えましょう。
【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?
戸籍謄本はいつ更新される?
戸籍謄本は、身分事項に変更があった場合に更新されます。
具体的には、出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組などの事由が発生した場合に、戸籍にその内容が記載され、戸籍謄本も更新されます。
例えば、子どもが生まれた場合、その子どもの氏名、生年月日、父母の名前などが戸籍に記載されます。婚姻した場合、夫婦の戸籍が新たに作成され、本籍、氏名などが新たに記載されます。離婚した場合、離婚の事実が戸籍に記載されます。死亡した場合、死亡の事実が戸籍に記載され、その戸籍から除籍されます。
このように、戸籍は常に最新の身分関係を反映するように更新されています。
ただし、戸籍の更新には時間がかかる場合があります。例えば、婚姻届や離婚届を提出してから、戸籍にその内容が反映されるまでには、数日から数週間程度かかることがあります。
戸籍謄本の有効期限は?
戸籍謄本自体に有効期限はありません。
しかし、提出先によっては、「発行から3ヶ月以内」など、有効期限が定められている場合があります。これは、戸籍謄本に記載されている情報が最新のものであることを保証するためです。
例えば、銀行預金の相続手続きなどの手続きにおいては、有効期限が定めらた戸籍謄本の提出が求められることが一般的です。
もし有効期限が過ぎてしまった場合は、再度戸籍謄本を取得する必要があります。また、手続きの案内に有効期限の表記がない場合でも、あまりにも古い戸籍謄本は、提出先によっては受け付けてもらえない場合があります。
提出先に有効期限が定められているかどうかを確認し、期限内に取得した戸籍謄本を提出するようにしましょう。
戸籍謄本の内容に誤りがあったらどうする?
戸籍謄本の内容に誤りがある場合、放置せずに訂正する必要があります。誤りの内容にもよりますが、市区町村役場または家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
例えば、氏名や生年月日などの基本的な情報に誤りがある場合は、市区町村役場に申し出て、訂正の手続きを行います。この場合、誤りの原因となった書類や、正しい情報を証明する書類などを提出が必要な場合があります。
一方、重大な誤りがある場合や、市区町村役場での訂正が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、訂正の許可を得る必要があります。例えば、親子関係に誤りがある場合などが該当します。
いずれの場合も、訂正には時間と手間がかかる場合がありますので、できるだけ早く手続きを行うようにしましょう。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
相続登記でお困りの方へ
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
司法書士への無料相談はこちら
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
無料相談実施中!
お客さまの声
相続手続きガイド
相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
事務所概要

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
住所
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
主な業務地域
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!




