不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
死亡届と埋火葬許可証とは?人が亡くなって最初に必要な手続きを解説
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年2月7日
死亡届・埋火葬許可証とは?
死亡届とは、人が亡くなったことを市区町村役場に届け出る書類で、これにより戸籍や住民票に死亡が記載され、公的に死亡が認められます。一方、埋火葬許可証は火葬や埋葬を行うための許可を証明する文書で、火葬場での火葬時や、その後に遺骨を墓地に納骨する際に必要となります。
人が亡くなった際に必要となる最初の公的手続き
人が亡くなったら、最初に行うべき公的手続きが死亡届の提出です。
死亡届は戸籍法で義務付けられており、原則として亡くなった事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。
この届出により役所で死亡が登録され、年金停止や健康保険などその後の各種行政手続きが進められるようになります。
また、死亡届の提出と同時に火葬または埋葬の許可証である埋火葬許可証を取得する必要があり、これらが遺族が最初に直面する重要な公的手続きとなりま
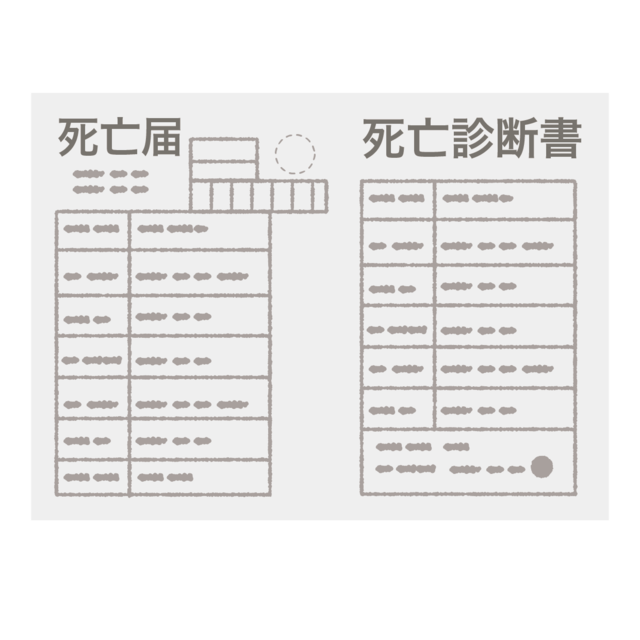
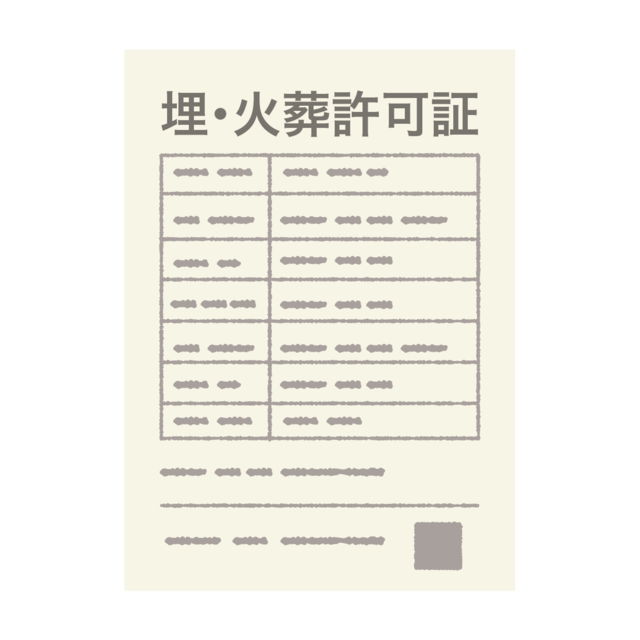
死亡届と埋火葬許可証の役割の違い
死亡届と埋火葬許可証は目的も役割も異なります。
死亡届は人が死亡した事実を役所に届け出て法的に認めてもらうためのもので、これにより戸籍に死亡が記載され、年金の停止や世帯主変更など亡くなった方に関する行政手続きが始められます。一方、埋火葬許可証は遺体を火葬または埋葬してよいという許可を証明する書類です。
死亡届が受理されると役所で火葬許可証が発行され、それを火葬場に提出しないと火葬はできません。また火葬後にはその許可証に火葬済の印が押され、埋葬許可証として遺骨の納骨時に必要になります。
つまり、死亡届は死亡の届出、埋火葬許可証は遺体の処置許可という違いがあり、役割は異なりますがどちらも葬送には欠かせない手続きです。
| 項目 | 死亡届 | 埋火葬許可証 |
|---|---|---|
| 目的 | 人が死亡した事実を役所に届け出て法的に認めてもらう | 遺体を火葬または埋葬してよいという許可を証明する |
| 役割 | 戸籍に死亡を記載、年金停止や世帯主変更など行政手続きの開始 | 火葬場での火葬実施、遺骨の納骨時に必要 |
| 効果 | 公的に死亡が記録・証明される | 火葬・埋葬の許可が得られる |
死亡届に関する手続きの詳細
死亡届とは、人が死亡したことを市区町村に届け出るための書類および手続きで、戸籍法に基づく義務です。これを提出することで公的に死亡が記録・証明され、亡くなった方の戸籍には死亡の事実が記載され、住民票も抹消されます。
これにより年金や健康保険など各種社会保障の停止、相続手続きなど死亡後の諸手続きが円滑に進むようになります。つまり死亡届の目的は、法的に死亡を認めてもらい、その後の行政・法的手続きの土台を作ることにあります。
提出期限と提出先
死亡届の提出期限は法律で定められており、死亡の事実を知った日から7日以内とされています。国内で亡くなった場合は死亡を確認した日を含めて7日目までが期限ですが、7日目が役所の休日に当たる場合は翌開庁日まで提出できます。
国外で亡くなった場合は事実を知った日から3ヶ月以内が提出期限です。
【提出先】以下のいずれか一箇所に提出します。
- 亡くなった方の死亡地の役場
- 亡くなった方の本籍地の役場
- 届出人の住所地の役場
役場の戸籍窓口が担当で、通常365日24時間受け付けています。夜間や休日は当直受付になりますが届出は可能です。ただし、深夜・休日の届出は担当職員不在で手続きに時間がかかることもあるため、可能であれば平日昼間に届け出るのが望ましいでしょう。
死亡届の提出期限
| 状況 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 国内で死亡 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 7日目が役所の休日の場合は翌開庁日まで可 |
| 国外で死亡 | 死亡の事実を知った日から3ヶ月以内 | 日本大使館・領事館または帰国後に提出 |
| 罰則: 正当な理由なく届出を怠ると5万円以下の過料 | ||
死亡届の提出先
| 提出先 | 詳細 |
|---|---|
| 死亡地の市区町村役場 | 亡くなった場所の市区町村役場 |
| 死亡者の本籍地の市区町村役場 | 故人の本籍がある市区町村役場 |
| 届出人の住所地の市区町村役場 | 届出をする人の住所地の市区町村役場 |
| ※戸籍窓口が担当で、通常365日24時間受け付け可能 | |
誰が提出できる?(届出人になれる人の範囲)
死亡届を提出できる人は法律で定められています。戸籍法第87条によれば、以下の順序と範囲で届出義務者が定められています。
【届出義務者】
- 同居の親族(故人と生計を共にしていた家族)
- その他の同居者(親族以外でも一緒に住んでいた人)
- 家主、地主または家屋管理人・土地管理人(故人が借家住まいなら大家さん等)
上記以外でも、別居の親族(遠方の親族)や後見人・保佐人・補助人・任意後遺後見人などの法定代理人も届出人になれます。つまり親族以外でも、故人と同居していた人や住居の管理者、法的な保護者的立場の人であれば届け出可能です。実務上は多くの場合、家族が届出人となりますが、家族がいない場合や事情で難しい場合は上記のような関係者が代わりに提出できます。
なお、死亡届は届出人本人が役場に持参するのが原則ですが、届出人が署名捺印した死亡届を他の人が代理提出することも可能です。例えば家族が用紙に記入・署名し、葬儀社のスタッフが役所に持っていくケースもよくあります。この場合でも届出人はあくまで署名した家族であり、届け出そのものは有効です。
必要書類と記入方法(死亡診断書との一体書式)
死亡届の提出には以下の書類等が必要です。
【必要書類】
- 死亡届書(届書)
- 死亡診断書(または死体検案書)
- 届出人の認印(念のため)
- 届出人の身分証明書(念のため)
多くの場合、A3サイズの用紙で左半分が死亡届、右半分が死亡診断書という一体形式になっています。病院で亡くなった場合は医師が右側の死亡診断書欄に記入済みの用紙を渡されるので、左半分の死亡届欄に故人と届出人の情報を記入します。記入内容は故人の氏名・生年月日・死亡日時・死亡場所、住所や本籍、届出人の氏名・住所・続柄などです。届出人の署名欄は自署が必要です。
死亡診断書と死体検案書の違い 死亡診断書は病気や老衰など自然な原因で亡くなった場合に医師が発行します。死体検案書は事故死や不明死など医師の診療下にない状況で亡くなった場合に警察の検視医などが発行します。いずれも効力は同じで、死亡届にはどちらか一方が必要です。
死亡届の提出期限
| 状況 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 国内で死亡 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 7日目が役所の休日の場合は翌開庁日まで可 |
| 国外で死亡 | 死亡の事実を知った日から3ヶ月以内 | 日本大使館・領事館または帰国後に提出 |
| 罰則: 正当な理由なく届出を怠ると5万円以下の過料 | ||
死亡届の提出先
| 提出先 | 詳細 |
|---|---|
| 死亡地の市区町村役場 | 亡くなった場所の市区町村役場 |
| 死亡者の本籍地の市区町村役場 | 故人の本籍がある市区町村役場 |
| 届出人の住所地の市区町村役場 | 届出をする人の住所地の市区町村役場 |
| ※戸籍窓口が担当で、通常365日24時間受け付け可能 | |
死亡届が受理された後の流れ
役所に死亡届を提出すると、内容がチェックされ、問題なければ死亡届が受理されます。受理されると役所は死亡の事実を戸籍に記載します。亡くなった方の戸籍に「○年○月○日死亡」と記載され、法律的に死亡が登録されます。戸籍への記載は、本籍地が提出先の役所でない場合は役所間の連絡により行われるため、完了までに数日から1週間程度かかることがあります。
死亡届が受理されると同時に、埋火葬許可証(火葬許可証)が発行されます。死亡届提出の際に火葬の日時・場所を申請しておけば、許可証が即日交付されるのが一般的です。この許可証は火葬や納骨の際に必要なため、大切に保管しておきます。
なお、死亡届を提出した役所では死亡に伴う他の手続きについても案内があります。例えば国民健康保険の葬祭費請求や介護保険証の返却、年金受給停止の届出などを一緒に行える場合があります。最近ではおくやみ窓口といって、死亡後の各種届出をワンストップで支援してくれる窓口を設けている自治体もあります。死亡届提出後、必要に応じて担当者に確認してみると良いでしょう。
埋火葬許可証に関する手続きの詳細
埋火葬許可証は死亡届の提出と同時に発行申請を行うのが一般的です。具体的な手順は以下の通りです。
1. 火葬の日時・場所を決める 葬儀社や火葬場に相談し、火葬を行う斎場と日時を決定します。火葬は法律上、死亡後24時間を経過しないと行えないため、通常は翌日以降の日程で調整されます。日時や場所が決まっていないと火葬許可証は発行できないため、届出時までに必ず火葬場の予約を済ませておく必要があります。
2. 死亡届と火葬許可申請を行う 死亡届を役場に提出する際に、火葬許可証の申請も行います。自治体によっては別途「火葬許可申請書」の提出が必要ですが、提出先は死亡届と同じく市区町村役場です。申請書は役場窓口で入手できるほか、自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります。一方で、自治体によっては死亡届を受理すれば自動的に許可証を発行してくれるところもあり、その場合申請書は不要です。
3. 火葬許可証の交付を受ける 書類に不備がなければ、その場で火葬許可証が交付されます。申請から交付までは通常、即日完了します。交付された火葬許可証は火葬の日まで紛失しないよう注意して保管しましょう。
4. 火葬当日に提出・返却 火葬当日、火葬許可証を火葬場の窓口に提出します。火葬場側はこの許可証がないと遺体を受け入れてくれません。無事に火葬が終了すると、火葬場の係員から許可証が返却されます。そこには「火葬執行済」等の証明印が押されています。この印が押された許可証こそが埋葬許可証となり、引き続き遺骨の埋葬・納骨に必要な書類となります。
5. 納骨・埋葬時に提出 遺骨は多くの場合、四十九日法要の際にお墓に納めます。その納骨時に埋葬許可証を墓地管理者へ提出します。この書類がないと墓地・霊園で遺骨を受け入れてもらえないため、必ず持参しましょう。なお、遺骨を分けて複数の場所で納める分骨をする場合は、火葬場で分骨証明書を発行してもらう必要があります。
埋火葬許可証が必要となる場面
埋火葬許可証が必要になる主な場面は火葬時と納骨・埋葬時です。
火葬を行うとき 火葬炉に遺体を入れる前に、火葬場に火葬許可証を提出しなければなりません。火葬許可証なしでは火葬そのものが法律上できないため、必ず提示を求められます。
納骨・埋葬をするとき 火葬後、埋葬許可証(火葬済みの印が押された火葬許可証)を墓地や納骨堂の管理者に提出します。これによって正式に遺骨を埋葬できるようになります。お墓を新たに建てる場合でも、埋葬許可証の提出が必要です。提出がないと「その遺骨は正式に火葬された証明がない」と判断され、納骨できません。
改葬(お墓の引っ越し)をするとき 一度納骨した遺骨を別の墓地に移す場合、改葬許可申請に埋葬許可証が必要になることがあります。改葬許可証の取得時に前の埋葬許可証を提出するケースもありますので、納骨後も大事に保管しておきましょう。
埋火葬許可証は火葬から埋葬まで一貫して必要となる重要書類です。この書類が揃って初めて故人を法律に則って送り出すことができます。死亡届が提出されなければ火葬許可証が発行されず火葬ができず、火葬許可証(埋葬許可証)がなければ遺骨を納めることもできません。公的手続きとセレモニーの両面で欠かせない存在といえます。
紛失した場合の対応(再交付の手続き)
埋火葬許可証を紛失してしまった場合でも、慌てずに対応すれば再発行してもらうことが可能です。
火葬前に紛失した場合 まずは葬儀社などに預けていないか確認します。もし見当たらなければ、死亡届を提出した同じ市区町村役場で再発行の申請を行います。再発行には窓口で所定の火葬許可証再交付申請書を記入し、届出人の本人確認書類などを添えて提出します。自治体によっては手数料がかかる場合があります。再発行申請すると、その場で新しい火葬許可証を出してもらえますので、それを使って火葬を行います。
火葬後(埋葬許可証)を紛失した場合 まず遺骨を納めた桐箱などに入っていないか確認します。多くの場合、押印済みの埋葬許可証は骨壺を収める箱に一緒に入れて保管されています。また一時的にお寺などに遺骨を預けている場合は、お寺に預けていないか確認しましょう。それでも見つからない場合は、やはり死亡届を出した役所で再交付申請を行います。
注意点として、自治体によって火葬許可証の保存期間(再発行対応期間)を5年程度に定めていることがあります。発行から5年以上経過していると再交付できない場合があり、その場合は火葬を行った火葬場で火葬証明書(火葬の事実証明)を発行してもらい、それをもって埋葬許可の代わりとする手続きを取ります。いずれにしても、まずは役所に相談するとよいでしょう。
再交付申請は原則として最初に死亡届を提出した人(届出人)が行います。届出人が既に亡くなっている場合などは、その配偶者や直系親族が申請できるケースもあります。必要書類は自治体ごとに異なるため、事前に役所へ問い合わせて確認しましょう。
死亡届提出から埋火葬許可証発行までの一連の流れ
死亡から火葬までの具体的な流れを時系列でまとめます。
1. 医師から死亡診断書を受け取る 病院で亡くなった場合、その場で担当医から死亡診断書を発行してもらいます。事故などの場合は警察医の検視後に死体検案書が交付されます。まずはこの死亡を証明する書類を受け取ることが出発点です。
2. 死亡診断書と一体になった死亡届を市区町村へ提出 死亡診断書が用意できたら、用紙の死亡届欄に必要事項を記入し、市区町村役場の戸籍係窓口に提出します。届出人の認印と身分証を持参し、亡くなった日から7日以内に届け出ましょう。提出時に火葬許可証の申請も同時に行います。
3. 役所が死亡届を受理し、埋火葬許可証を発行 窓口で死亡届が受理されると、直ちに火葬許可証が発行されます。事前に決めておいた火葬日時・場所が許可証に記載されます。問題がなければその日のうちに火葬許可証を受け取ることができます。これで役所での手続きは完了です。受け取った埋火葬許可証は火葬まで大切に保管します。
4. 火葬場・霊園に提出して火葬・埋葬を実施 火葬当日、遺族または葬儀社が火葬場の受付に火葬許可証を提出します。許可証確認後、火葬が執り行われ、終了後に火葬済の印が押されて返却されます。この返却された書類(埋葬許可証)を持って、49日などのタイミングでお墓に納骨します。納骨時には墓地の管理者に埋葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
実際には病院で亡くなった直後に葬儀社へ連絡し、並行して葬儀日程や火葬場予約を決めていくことになります。多くの場合、葬儀社が死亡届の提出や火葬場の予約を代行してくれるため、遺族は必要書類に記入・押印するだけで手続き自体はスムーズに進むでしょう。
死亡届と埋火葬許可証の両方が揃わないと進められない手続き
死亡届と埋火葬許可証のどちらか一方でも欠けると、その後の手続きが進められなくなります。
死亡届を提出していない場合 火葬許可証が発行されないため火葬そのものが行えません。仮に届出を怠ったまま火葬しようとしても、火葬場で許可証の提示を求められるためストップがかかります。また、死亡届が出されていない状態では戸籍上故人は「生存」扱いのままなので、年金の停止や相続手続きも開始できません。
埋火葬許可証が手元にない場合 遺体を火葬場に搬入できず、火葬後も遺骨を正式に埋葬できなくなります。
法的リスク 万一死亡届の提出を忘れていたり遅れたりすると、法律上は届出義務違反となり過料を科される可能性もあります。戸籍法では正当な理由なく届出が遅れると5万円以下の過料に処すと定められています。それだけでなく、死亡の届出がないと様々な行政サービスが止まらずに進行してしまい、遺族に不利益が生じます。例えば故人の年金が支給され続けてしまい、後から返還が必要になるとか、相続の手続きで戸籍に死亡記載がなく困るといった事態も起こりえます。
死亡届と埋火葬許可証は両輪です。必ず両者を揃えて初めて次のステップに進めることを念頭に置き、手続きを進めましょう。
死亡届と埋火葬許可証に関するよくある質問FAQ
死亡届はどこで入手できますか?
死亡届の用紙は市区町村役場の戸籍係でもらえます。また、多くの病院でも用意しています。通常は死亡診断書と一体になった形で病院から受け取るケースが多いです。
提出期限の「7日以内」は土日や祝日も含みますか?
はい、7日以内には土日祝日も含まれます。死亡した事実を知った日を1日目として数え、カレンダー通り7日目までが期限です。ただし7日目が役所の閉庁日に当たる場合、実務上は翌開庁日まで受付可能とされることが多いです。
死亡届を提出できるのは家族以外でも可能ですか?
可能です。故人と同居していた親族や親族以外の同居人、故人の家主や土地・家屋の管理人、後見人などが該当します。また家族が届出書に署名捺印すれば、葬儀社など第三者が使者として役所に提出することも可能です。
埋火葬許可証は交付までどのくらい時間がかかりますか?
ほとんどの場合、死亡届を提出したその場で即日交付されます。役所の窓口で書類に不備がなければ、火葬許可証をそのまま手渡してもらえます。手続き自体は数十分程度で完了するでしょう。
許可証を紛失したらどうすればいいですか?
紛失しても再発行は可能ですので落ち着いて対応しましょう。火葬前であれば、まず葬儀社が預かっていないか確認し、それでも無ければ死亡届を出した役所で再発行申請をします。火葬後で埋葬許可証を失くした場合も同様に役所で再交付してもらいます。ただし発行から年月が経っている場合(5年程度)、自治体で記録を保存していないことがあります。その際は火葬場に記録が残っていれば火葬証明書を発行してもらい、代替とします。
火葬・埋葬の予約は死亡届提出前にできますか?
はい、むしろ事前に火葬場の予約をしておく必要があります。火葬許可証を発行してもらうには火葬日時と場所の情報が必須なので、届出時までに斎場の予約や日程調整を済ませましょう。
死亡届や許可証の手続きは葬儀社が代行してくれますか?
多くの葬儀社では死亡届の提出や火葬許可証の申請を代行しています。葬儀社が代行する場合でも、死亡届の届出人欄にはご家族などが署名する必要がありますが、役所への提出作業は葬儀社スタッフが行ってくれるので安心です。
海外で死亡した場合も同じ手続きですか?
基本的な流れは似ていますが、手続き先と期限が異なります。現地の日本大使館・領事館で在外死亡届を提出するか、帰国後に故人の本籍地または届出人住所地の市区町村役場に死亡届を提出します。提出期限は「死亡の事実を知った日から3ヶ月以内」です。
死亡診断書と死体検案書はどう違うのですか?
どちらも死亡を証明する書類ですが、発行される状況が異なります。死亡診断書は医師が診療中の患者さんが自然な経過で亡くなった場合に発行するものです。一方、死体検案書は事故死や突然死など医師の診療管理下以外で亡くなった場合に発行されます。ただし死亡届を出す際には両者の扱いは同じであり、どちらか一方を添付すれば届出として受理されます。
死亡届を提出しないとどうなりますか?
死亡届は法律上の義務ですので、提出しないままでいると罰則の対象になり得ます。戸籍法では正当な理由なく届出を怠ると5万円以下の過料に処すると規定されています。また罰則以上に深刻なのは実務上の支障です。死亡が戸籍に記載されないと、故人の年金受給停止手続きができず不正受給になってしまう、生命保険の死亡保険金請求に必要な公的証明が取れない、相続の手続きで戸籍謄本に死亡の記載が無いため進められない等、多方面で問題が起こります。さらに火葬許可証も発行されないため故人を火葬・埋葬すること自体が違法となってしまいます。
まとめ
以上、初めて葬儀を行う方にも分かりやすいように死亡届と埋火葬許可証の基礎知識と手続きの流れを解説しました。悲しみの中での手続きは大変ですが、ここで述べたポイントを押さえておけば大丈夫です。
迅速に死亡届を提出し、埋火葬許可証を取得することで、法的にもしっかりと故人を送り出せます。役所や葬儀社の力も借りながら、落ち着いて進めてください。わからないことがあれば遠慮なく専門家に相談し、適切なサポートを受けることも大切です。
最後にもう一度強調しますが、「死亡届」と「埋火葬許可証」が葬儀手続きの要です。この二つさえきちんと済ませれば、あとの手続きは円滑に進むでしょう。大切な故人を安心して送り出すためにも、法律に沿った確実な手続きを心がけてください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
相続登記でお困りの方へ
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
司法書士への無料相談はこちら
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
無料相談実施中!
お客さまの声
相続手続きガイド
相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
事務所概要

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
住所
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
主な業務地域
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!



