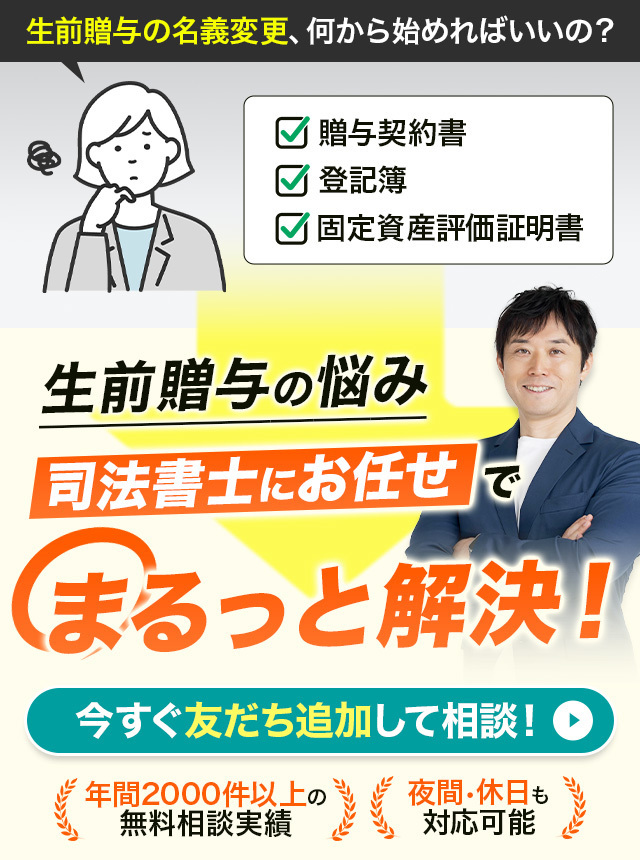不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
0120-670-678
受付時間 | 9:00〜18:00 (土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料で承ります!
贈与税がかからないで家や土地などの不動産を名義変更することはできる?
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月15日
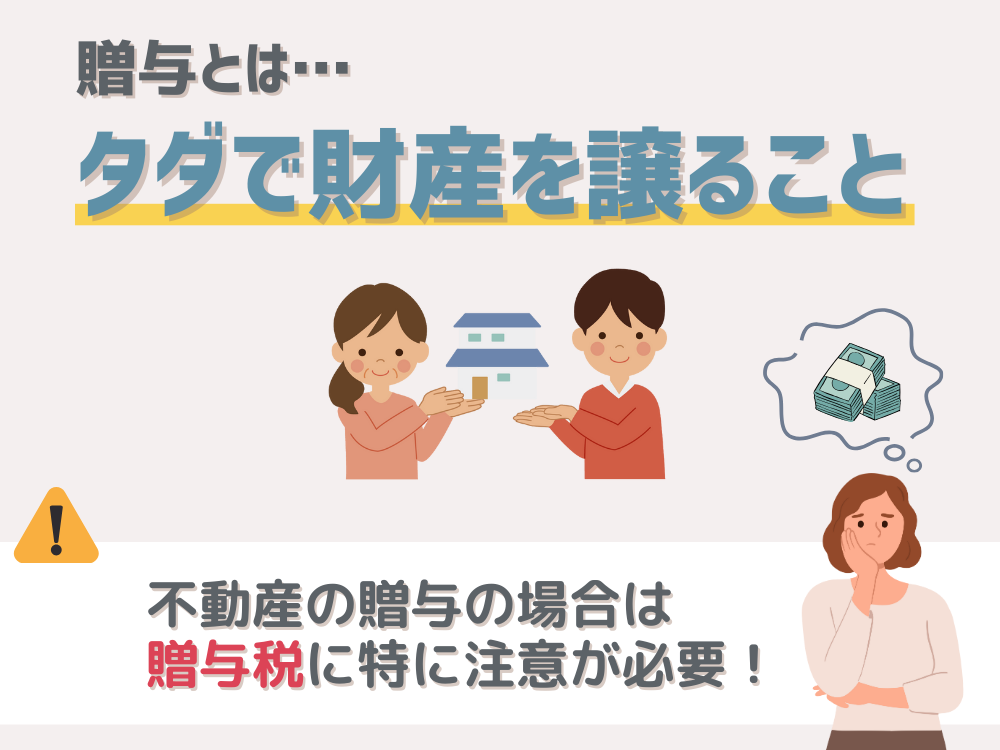
そもそも贈与とは?知っておくべき贈与税の知識
贈与とはタダで財産を譲ること
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりません。(別途、所得税等が課税されます。)
年間、基礎控除額である110万円を超える財産の贈与があった場合、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
1年間で110万円超える財産の贈与を受けた(タダで貰った)場合は、翌年に贈与税が課税されます。贈与税の申告が必要です。
贈与税は贈与財産が高額になると高税率(最大55%)になりますので土地やマンションなどの贈与を受け、名義変更する際には注意が必要です。名義変更手続き前に、税理士に確認することをお勧めいたします。
毎年110万円以内の贈与であれば、贈与税が控除(基礎控除)されますので、年間110万円以内の財産の贈与には贈与税は課税されません。
評価額が110万円を超える土地や建物であっても、毎年110万円以内の持分割合で贈与をすれば基本的には贈与税がかからないことになります。ただし、毎年繰り返しの贈与については、定期贈与と認定されてしまうと贈与税が課税されます。
その他、贈与税がかからず名義変更する方法としては、相続時精算課税や配偶者控除の特例制度の利用が考えられます。
不動産贈与税が「かからない」非課税・特例制度の徹底比較
不動産の生前贈与では、財産が高額になるため暦年贈与の基礎控除(年間110万円)だけでは対応が難しく、最大55%もの高税率が課されるリスクがあります。そのため、贈与税を合法的に非課税または大幅に軽減するには、税法で定められた特定の非課税特例の適用が不可欠となります。
ただし、非課税制度を利用する際に最も重要なのは、各制度のメリットだけでなく、特有のデメリットや適用要件を事前にしっかり理解し、手続きを正確に行うことです。
特に不動産贈与では、小規模宅地等の特例との兼ね合いなど、複雑なトレードオフが生じるため、慎重な検討が必要です。
主要な不動産贈与税非課税・控除制度の比較
| 制度名 | 非課税(控除)限度額 | 適用要件 | 最大のメリット | 最大のデメリット |
|---|---|---|---|---|
| 暦年贈与 (基礎控除) | 年間 110万円 | 贈与財産の種類を問わない。不動産は持分割合で調整。 | 手続きが比較的容易。 | 定期贈与認定リスクが最も高い。長期的な移転が必要。 |
| 相続時精算課税制度 | 特別控除 2,500万円 + 年間基礎控除 110万円 | 60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与。 | 贈与時の評価額で固定。年110万円の贈与は相続加算なし。 | 小規模宅地等の特例不適用。一度選択すると暦年課税に戻れない。 |
| 居住用不動産配偶者控除 | 2,000万円 (基礎控除と合計2,110万円) | 婚姻期間20年以上。居住用不動産。翌年3月15日までに居住。 | 高額な自宅を贈与税ゼロで移転可能。 | 同じ夫婦間では一生に一度のみ。要件を満たさないと適用不可。 |
| 住宅取得等資金の贈与 | 最大1,000万円 (期限あり) | 父母・祖父母から18歳以上の直系卑属へ。新築・取得資金。 | 相続時精算課税制度との併用が可能。 | 適用期限と住宅の品質・面積要件が厳格。 |
暦年贈与(基礎控除110万円)『誰でも利用可能』
暦年贈与による不動産の生前贈与
暦年贈与は、毎年110万円の基礎控除を利用し、その範囲内であれば贈与税が非課税となる最も一般的な手法です。不動産のように評価額が110万円を大きく超える財産であっても、毎年110万円以内になるよう不動産の持分割合を計算し、その持分のみを贈与することで、贈与税を発生させずに段階的な名義変更が可能となります。
実務上の課題
この手法の最大の課題は、不動産の評価額を正確に算定しなければならない点です。土地は路線価、建物は固定資産評価額を基準として、贈与する持分割合が110万円以下に収まるよう慎重に計算する必要があります。また、不動産の移転には毎年所有権移転登記が必要となり、その都度登録免許税や司法書士費用が発生します。
最大のリスク:定期贈与認定
しかし、暦年贈与は定期贈与と認定されるリスクが最も高い手法でもあります。税務署に否認されると、過去の贈与総額が一括で課税されることになるため、単純に「毎年110万円を贈与すればよい」という認識は危険です。安全性を確保するには、専門家によるリスク回避対策の実施が不可欠となります。
相続時精算課税『親子間・祖父母と孫で利用可能』
制度の基本概要
相続時精算課税制度は、親(60歳以上)から子・孫(18歳以上)への贈与について、累計2,500万円までが非課税となる特例です。
贈与した財産は贈与時の価格で評価され、贈与者が死亡した際の相続財産に合算される仕組み(精算課税)となっています。2500万円を超える場合は、超えた額の20%に贈与税が課税されますが、相続の際に精算となります。特例を利用するには贈与を受けた翌年に申告・届出が必要です。
2024年税制改正による劇的な変化
2024年(令和5年度税制改正)の施行により、この制度は劇的に使いやすくなりました。従来の2,500万円の特別控除枠に加え、年間110万円の基礎控除枠が新設されました。この年間110万円以下の贈与については、贈与税が課税されないだけでなく、相続時に相続財産へ加算する必要がなくなり(生前贈与加算の対象外)、さらに贈与税の申告も不要となりました。
これにより、相続時精算課税は実質的に「暦年贈与のメリット」と「多額の控除枠」を併せ持つ非常に強力な制度となりました。特に、将来的な値上がりが予想される不動産や収益を生む賃貸不動産を贈与する場合、贈与時の価格で相続税の計算に含めることができるため、相続税対策として有効です。
不動産贈与における致命的なデメリット
相続時精算課税を選択する際には、極めて重大なデメリットを理解しなければなりません。それは、この制度によって贈与された土地や建物は、相続税の計算における「小規模宅地等の特例」の適用対象から外れてしまうという点です。
小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用や事業用に使われていた宅地について、評価額を最大80%減額できる、日本の相続税対策において最も強力な節税策です。もし贈与を検討している不動産がこの特例の適用要件を満たす可能性があり、かつ相続財産全体が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える見込みがある場合、相続時精算課税を利用して贈与することで、将来的に相続税が大幅に増加するリスクが生じます。
慎重な判断が必要
したがって、相続時精算課税は万能な節税策ではありません。必ず税理士による相続税のシミュレーションを経て、小規模宅地等の特例を放棄するメリットが、2,500万円の特別控除と年間110万円の基礎控除を上回るかどうかを判断する必要があります。一度選択すると暦年課税に戻れないため、制度選択は慎重に行うべきです。
配偶者控除『夫婦間で利用可能』
高額な居住用不動産を贈与税ゼロで名義変更したい場合、夫婦間の居住用不動産の贈与特例(配偶者控除)が最も強力な選択肢となります。
制度概要
この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合に、2,000万円までが贈与税の課税対象から控除されるものです。暦年贈与の基礎控除110万円と合わせると、合計2,110万円までが非課税となります。結婚20年以下の場合や、自宅以外の別荘や収益物件などの場合は利用できません。
配偶者控除を利用できれば、2,000万円以下の自宅の贈与であれば贈与税は課税されません。家全体の評価額が2,000万円を超えても、例えば3,000万円のマンションの2分の1の割合(贈与する分の評価額は1,500万円)であれば贈与税がかからず名義変更手続きが可能です。また、自宅の家屋と土地はまとめて贈与を受ける必要はありません。一定の要件を満たせば、土地のみ家屋のみの贈与も対象です。
特例を利用するには贈与を受けた翌年に申告が必要です。
適用要件(すべて必須)
- 婚姻期間:夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 贈与財産の種類:贈与された財産が、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
- 居住要件:贈与を受けた年の翌年3月15日までに、受贈者(贈与を受けた配偶者)がその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
重要な制限事項
この特例は、同じ夫婦間では一生に一度しか適用を受けることができません。
住宅取得等資金の贈与の特例『親子間・祖父母と孫で利用可能』
制度概要
この特例は、父母や祖父母(直系尊属)が18歳以上の子や孫に対し、自宅を新築・取得または増改築等するための資金を贈与する場合に、最大1,000万円までが非課税となる制度です(省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで)。
主な特徴
- 他制度との併用可能:暦年贈与や相続時精算課税制度との併用が可能であり、特に若年層が住宅を取得する際の資金援助として活用されます
- 期限と要件の厳格性:適用期限が定められており(令和6年1月1日から令和8年12月31日まで)、住宅の要件(面積や品質)も厳格に定められています
贈与による名義変更手続きの無料相談はこちら
暦年贈与で問題となる「定期贈与」認定リスクと回避マニュアル
不動産の持分や、その購入資金を暦年贈与として毎年継続的に行う場合、税務署から「定期贈与」と認定されるリスクが常に伴います。これは、贈与税を非課税にするための「守りの戦略」として、最も重要な知識です。
定期贈与と税務署の判断基準
定期贈与とは(計画贈与)
「定期贈与」とは、最初から「毎年一定額を〇年間にわたって贈与する」という単一の契約が成立していたと見なされることです。この認定がされると、個々の年の贈与額が110万円以下であっても、契約総額(例:1,100万円)に対して初年度に一括して贈与税が課税されます。これは、贈与計画がすべて崩壊し、多額の追徴課税を受けることを意味します。
連年贈与との違い
これに対し、毎年単発の契約に基づき行われる贈与は「連年贈与」と呼ばれ、これは合法的な暦年贈与です。
税務署の判断基準
税務署は、贈与者の預金管理状況や贈与のタイミング、契約書の有無などを総合的に見て、実質的に単発の契約が毎年行われていたのか、それとも最初から総額の贈与が目的であったのかを判断します。
申告漏れによるペナルティ(加算税)の脅威
不動産贈与のように高額な財産が関わる場合、申告漏れや隠ぺいが認定された際のペナルティは極めて甚大です。
税務調査により贈与税の申告漏れが発覚した場合、本来納めるべき税額に加え、以下の加算税が課されます。特に、悪質と認定される「重加算税」の税率は、本来の税率と相まって、財産価値を大きく超える負担となり得ます。
税務署に贈与の事実や金額を隠蔽・仮装したと判断された場合、無申告加算税の代わりに40%もの重加算税が課されます。贈与税の最高税率55%にこの40%のペナルティが加わると、財産移転の目的が完全に失われるため、専門家による適正な手続きと申告代行が必須となります。
定期贈与認定を回避するための具体的な対策
税務調査で定期贈与とみなされないためには、以下の手続きを毎年徹底することが求められます。
- 贈与契約書の毎年作成と保管
毎年、贈与を行う都度、その年の贈与財産、金額、日付を明記した贈与契約書を作成し、贈与者と受贈者が署名・押印し、保管します。これは、その年の贈与が独立した契約に基づくものであることを証明する最も重要な証拠となります。
- 贈与の時期、金額、財産の種類を分散させる
毎年同じ日に、同じ金額(例:きっかり110万円)を同じ財産(現金)で贈与し続けると、計画的で連続した贈与とみなされやすくなります。時期をずらしたり、金額を微調整したり、現金だけでなく不動産の持分や株式などを混ぜたりすることで、「単発性」を強調します。
- 受贈者による財産の自由な管理(名義預金回避)
贈与された資金や不動産を、贈与者(親など)が依然として実質的に管理している場合、「名義預金」と認定されます。贈与後の財産は、通帳、印鑑、カードをすべて受贈者本人が管理し、自由に入出金や運用を行うことが必須です。
- 戦略的に基礎控除を超過して申告する
贈与額をあえて110万円をわずかに超える額(例:120万円)に設定し、贈与税の申告・納付を毎年行うという戦略があります。これは、わずかな税負担を受け入れる代わりに、「年間110万円の非課税枠を狙った連続贈与ではない」という強い証拠となり、定期贈与と認定されるリスクを大幅に下げることができます。
※重要な注意事項
上記の対策は実務上一般的に推奨されている手法ですが、税務上の効果や認定回避を保証するものではありません。個別の状況や最新の税制に応じた適切な判断が必要となるため、必ず税理士等の専門家にご相談の上、実行してください。
贈与税の申告義務と非課税制度の誤解によるペナルティ
贈与税が「かからない」状況であっても、多くの非課税特例は、適用を受けるために税務署への申告が義務付けられています。この申告義務の不履行は、特例の適用が否認されるだけでなく、重いペナルティの対象となります。
非課税特例利用時の申告義務
申告が必要な特例と申告期限
暦年贈与における年間110万円以下の贈与(ただし2024年以降の相続時精算課税基礎控除内の贈与を含む)を除き、相続時精算課税制度や夫婦間居住用不動産配偶者控除などの特例を利用する場合は、贈与税額がゼロであっても、期限内(贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日まで)に税務署へ申告書と添付書類を提出しなければなりません。
申告を怠った場合のリスク
この申告を怠ると、特例が適用されず、暦年課税の税率に基づき贈与税が課税されるリスクがあります。
贈与税以外に発生する不動産贈与の税金・費用
贈与税が非課税になったとしても、不動産の名義変更(所有権移転登記)には、贈与税以外の税金と実費が発生します。これらの費用を見落とすと、資金計画に狂いが生じるため、全体像の把握が重要です。
登録免許税
名義変更登記を行う際に、法務局へ納める国税です。
贈与による所有権移転の場合、原則として固定資産税評価額の2.0%が課されます。これは、相続による移転(0.4%)や売買による移転(原則2.0%、軽減措置適用で0.3%)と比較して高税率となることが多い点に注意が必要です。
不動産取得税
不動産を取得した際にかかる地方税(都道府県税)です。
贈与による取得は、原則として課税対象となります。税額は、固定資産税評価額を基に算出され、一般的な税率は3%または4%ですが、居住用宅地や住宅については特例により軽減措置が適用される場合があります。
夫婦間贈与特例や相続時精算課税を利用した場合でも、不動産取得税は原則として発生します。
その他、司法書士手数料および印紙税
不動産の名義変更登記は複雑な手続きを伴うため、通常は司法書士に依頼します。この際、司法書士への手数料が発生します。また、贈与契約書を作成する際、契約金額によっては印紙税(印紙代)が200円が発生します。
これらの実費も、贈与計画に含めておく必要があります。
令和5年度の贈与税の改正とは?2024年施行
令和5年度の贈与税の改正とは?
令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。改正については令和6年1月1日施行。
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算します。以前は相続開始前3年以内の贈与が対象でしたが4年間分が延長されるようになりました。
また、上記でも解説しましたが、相続時精算課税を利用した際に、暦年課税同様に、110万円までの基礎控除が控除されるようになりました。
名義変更手続きが難しいので専門家に依頼したい!
書類の収集が難しい!文書が作れない!役所へ行く時間がない!
ご自身で手続きできない場合(できそうにない場合)は、当センターにおまかせください!
書類の収集、作成、法務局の申請など基本的にすべて当センターで代行可能です。(贈与者の印鑑証明書の取得を除く。)
ご依頼いただいた場合は、お客様にやっていだく作業は基本的に以下の2つだけです。
- ①当センター用意した書類に記入や署名押印する
- ②印鑑証明書を役所から取得する(贈与する人のみ。貰う人は不要)
難しいやり取りは一切ございません。贈与者、受贈者とのやり取りも直接当センターが行います。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
2024年贈与税の改正
2024年の贈与税制改正により、生前贈与の常識が大きく変わりました。
改正の柱は2つ。1つ目は相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内は相続税の課税価格に加算されない点。従来の特別控除2,500万円との併用が可能で、110万円以下なら贈与税申告が不要になるケースもあります(初年度は選択届出書の提出必須)。また災害で被災した贈与不動産については、一定要件で相続時の加算価額を減額できる特例も創設されました。
2つ目は暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延長される点。相続開始日により加算対象期間が変わり、2031年以降の相続から完全に7年間が適用されます。重要なのは、110万円以下の贈与でも持ち戻しの対象となることです。
不動産の持分贈与では、毎年の登記で登録免許税2%が発生し、7年以内に相続が起きると「節税効果がないのに手続き費用だけ残る」コスト倒れのリスクがあります。相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻せないため、税理士・司法書士と連携した慎重な制度選択が不可欠です。
生前贈与による不動産名義変更の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
相続登記でお困りの方へ
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更(贈与・離婚・売買)の手続き詳細まとめ
不動産名義変更の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
司法書士への無料相談はこちら
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
無料相談実施中!
お客さまの声
相続手続きガイド
相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
事務所概要

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
住所
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
主な業務地域
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!