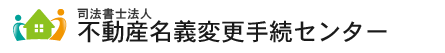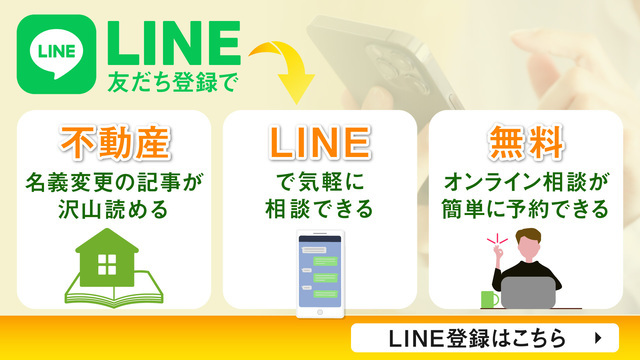不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
相続登記はなぜ義務化されたのか?背景や義務化により生じた問題点を司法書士が考察
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
相続登記はなぜ義務化された?義務化は必要だったのか?
相続登記の義務化とは?
相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人に変更する手続きです。これまで相続登記は任意とされてきましたが、2024年4月1日より法的に義務化されました。
この法改正は、不動産所有権の明確化と、それに伴う将来的な紛争の予防を目的としています。また、義務を怠った場合の罰則として、10万円以下の過料が科される可能性があることに注意が必要です。
社会的背景:深刻化する所有者不明土地問題
相続登記の義務化の背景には、「所有者不明土地」の増加という深刻な社会問題があります。これまで相続登記が義務ではなかったため、手続きが後回しにされたり、費用や手間をかけてまで登記を行う必要性を感じない相続人が多かったことが、この問題の大きな要因です。
特に地方では、土地の価値が低く、売却も困難な場合、相続登記へのインセンティブが働きにくい状況がありました。さらに、世代を超えて相続登記が行われないまま放置されることで、相続関係が複雑化し(数次相続)、いざ登記を行おうとしても、相続人の特定に多大な時間と費用がかかってしまうケースも少なくありません。
所在者不明土地の面積は、平成28年時点で約410万hrと推計されており、九州の総面積367万hrより広いとされています。所在者不明土地の経済損失は、単年で約1800億円(平成28年)と推計されています(国土交通省の資料より)。
https://www.mlit.go.jp/common/001201304.pdf
また、所有者が転居した際に住所変更登記を行わないことも、所有者不明土地の発生要因の一つです。所有者不明土地の増加は、公共事業やインフラ整備の妨げとなるだけでなく、民間取引や土地の有効活用を困難にするなど、地域社会に様々な悪影響を及ぼしています。
例えば、管理が行き届かないことで雑草が生い茂ったり、不法投棄されたり、老朽化した建物が倒壊する危険性も高まります。災害発生時には、復旧・復興事業の遅延にもつながるなど、その影響は広範囲に及びます。国土交通省の調査によると、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は約20%にも達するとされており、この問題の深刻さがうかがえます。
相続登記義務化の理由:所有者不明土地問題の解消に向けて
相続登記の義務化の主な目的は、所有者不明土地の増加を抑制し、土地の所有者を明確にすることにあります。相続が発生した場合、相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられました。
この義務は、2024年4月1日以前に相続が発生した未登記の不動産にも適用され、その場合は2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。この義務化によって、空き家問題や土地取引、公共事業の円滑な推進といった社会問題の解決が期待されています。
この法改正は、2021年(令和3年)の民法・不動産登記法改正(改正法施行は2024年)によって実現しました。
相続登記の義務化により生じた問題点
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決に寄与する一方で、新たな問題点や課題も生じさせています。
手続きの煩雑さと費用の問題
問題点の1つとして、手続きの煩雑さが挙げられます。相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票など、多くの書類を収集・準備する必要があり、特に法的手続きに不慣れな方にとっては大きな負担となります。
次に、費用の問題があります。相続登記には、書類の取得費用、登録免許税、そして司法書士に依頼した場合の報酬などがかかります。特に登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%とされており、高額な不動産を相続した場合には大きな負担となります。
さらに、相続関係が複雑なケース(例えば、相続人が多数いる場合や、数次相続が発生している場合)では、手続きがさらに煩雑になり、時間と労力がかかることが予想されます。
資産価値の高くない山林や農地については、手続きに要する費用が資産価値を上回り、費用倒れが生じる可能性も考えられます。
相続放棄が増える?
相続登記の義務化によって、相続放棄を選択する人が増加する可能性も指摘されています。
特に、価値の低い不動産や管理が困難な不動産を相続した場合、相続登記の費用や手間を考慮して相続放棄を選ぶケースが増えるかもしれません。
過去の古い相続は大変
過去に発生した相続についても義務化の対象となるため、すでに相続が発生してから長期間が経過しているケースでは、相続関係の調査や書類の収集が困難になることも懸念されます。3年という申請期限内にこれらの手続きを完了できない場合も出てくることが予想されます。
もっとも、法務省は、期限内に登記申請ができないことについて「正当な理由」がある場合には、過料を科さないとしています。「正当な理由」としては、相続人の人数が極めて多い場合、遺産分割協議が難航している場合、相続人が重病である場合、経済的に困窮している場合などが例示されています。
法務局の処理遅延
長年放置されていた土地が、相続登記の義務化により手続きが進むことにより、法務局の処理件数が増えたり、窓口の相談件数が増えることが考えられます。実際、2024年以降は法務局の審査期間が長くなっている印象があります。
民間業者の参入
相続登記の専門家は司法書士で、司法書士以外の者が相続登記の相談を受けたり、手続きを代理することは法律上できません。
相続登記の義務化に伴い、市場には低価格・短期間を売りにした民間サービスが急増しています。しかし、登記代理は司法書士の独占業務であり、無資格業者に依頼すると「手続不備」「物件漏れ」「情報漏えい」「高額追加費用」など多面的な危険が潜みます。
相続登記のような手続きが苦手な人はどうすればよい?
専門家(司法書士)に相談する
相続登記は専門的な知識と手続きが必要となるため、司法書士は相続人の皆様にとって重要な支援者となります。
司法書士は、戸籍謄本や住民票などの必要書類の収集、相続登記申請書や遺産分割協議書などの書類作成、法務局への申請手続きの代行など、煩雑な手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供します。
また、複雑な相続事案や法的な疑問についても、司法書士から専門的なアドバイスを受けることができます 。義務化された相続登記を期限内に行うためには、専門家である司法書士のサポートが不可欠と言えるでしょう。
簡略化された手続きと利用可能な支援
相続登記の義務化に伴い、手続きの簡略化や支援制度も導入されています。
例えば、「相続人申告登記」という制度は、遺産分割協議がすぐにまとまらない場合など、相続人が簡易な手続きで相続人であることを申告することで、相続登記の義務を一時的に履行できるものです。これは、相続人単独で行うことができ、全ての相続人の同意は必要ありません。ただし、相続人申告登記は、不動産の売却や担保設定に必要な完全な相続登記ではないことに注意が必要です。
また、戸籍謄本の収集を容易にする「戸籍の広域交付制度」も導入されています。さらに、不要な相続土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」も存在しますが、これには条件と費用がかかります。
まとめ
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決に向けた重要な一歩です。しかし、相続人の皆様にとっては、新たな義務と負担が生じることになります。
この制度を円滑に乗り切るためには、制度の内容を正しく理解し、必要に応じて簡略化された手続きや支援制度を活用することが重要です。
特に、複雑なケースや手続きに不安を感じる場合は、専門家である司法書士に早めに相談し、適切なサポートを受けることをお勧めします。これにより、過料のリスクを回避し、将来にわたって安心して不動産を管理・活用するための確実な一歩を踏み出すことができるでしょう。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
お問合せ・無料相談はこちら
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください!
無料相談実施中!
お客さまの声
相続手続きガイド
相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
事務所概要

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
住所
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
主な業務地域
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!